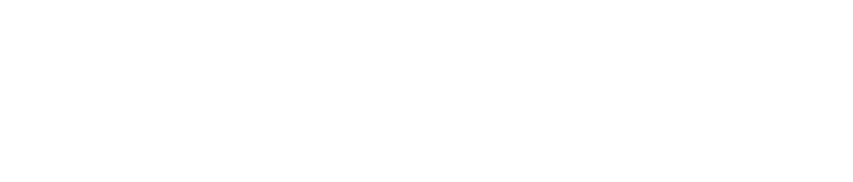東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 152
本阿弥 光悦
和歌色紙帖「橘の」
| 技法 | 紙本、墨、金泥下絵、淡彩 |
| 額 | 軸装 |
| サイズ | 21.3×19.1 cm |
| 鑑定書 | 田山方南識箱「陽明家傳来」 |
| 文献 | 三彩社編、 『季刊 古美術 20』 、三彩社、1967、pp.89-94、堀江知彦<清資料紹介19> 「光悦の書 -和歌色紙帖-」 |
HIGHLIGHT
歌の詠み : 皇太后宮大夫 俊成女哥 「橘の 匂ふ あたりの うたたねは 夢も むかしの そでのかぞする」 新古今和歌集 第三巻 夏歌より 245番 題しらず
通釈 : 橘の花の匂うあたりでするうたた寝は、見る夢も昔の袖の香りがするのだ。
補足 : 建仁三年(1203)四月以前、夫の源通具と共に行った歌合(通称「通具俊成卿女歌合」)に見える歌。
本作は、光悦の和歌色紙帖のうちの一作品である。本阿弥光悦は、近衛三藐院(信尹、1565-1614)、松花堂昭乗(1548-1639)とともに江戸初期の寛永の三筆として名高い。この三方は能書家の枠に捉われず、殊に光悦は書を高芸術にまで高めた。光悦の書の下絵描きは俵屋宗達が行っていたと言われているが本作は定かではない。光悦は書を、尊朝法親王により青蓮院流を授けられ、次いで近衛前久にも習った。このような特色のある書家に師事したことは和様書道の域を出させ、さらに上代様の平安朝の名筆への認識と探求は後の光悦流の装飾性の富む書体を生むもととなった。本作でも、肥痩豊かな律動的な書は眺める芸術といっても過言ではない。光悦の時代は桃山から江戸初期にかけて、同時期には狩野永楽や山楽が勇壮で絢爛な障壁画を描いた時に当り、時代を反映たものとも云える。堀江知彦によると「この帖は近衛家伝来ということですが、描かれている絵が、まことに細密ていねいなもので、あるいは、近衛家で色紙を用意して光悦に揮毫を依頼したものかも知れません。」と述べている。相見香雨はこの帖について、「これを寛永光悦という人もいると聞いていますが、私は慶長光悦で四十歳頃、ふだんから勉強家であり、筆まめであったこの人が、一番達者な頃の代表作であると判断します。」と語っている。<季刊 古美術20 堀江知彦「光悦の書 -和歌色紙帖-」より
尚、田山方南による識箱には「陽明家傳来」とあり、折紙の写しには、箱に陽明家印ありとあるも、新箱に改められており旧蔵印などは確認できない。本阿弥光悦は、日本刀の鑑定、研磨を行う家に生まれる。家業に従事しつつ、数寄者として書・陶芸・漆芸・能楽・茶の湯などに携わった総合芸術家であった。徳川家康より洛北鷹峯の地を拝領し、芸術村を築いたことでも知られる。