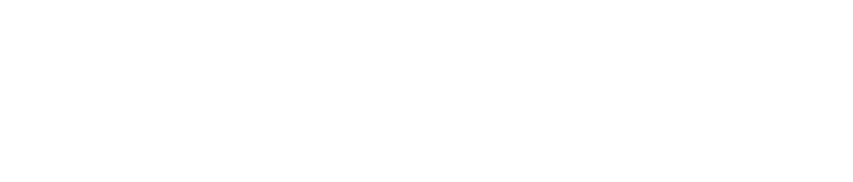東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 150
与謝 蕪村
人物図(三福対)
| 技法 | 紙本、彩色 |
| サイン | 左幅:左下に落款「四明」、白文方印「懶郎子」 朱文方印「朝滄」 中幅:右上に款「浪華長堤 四明山人画」、朱文方印「□□山人」 白文方印「渓漢山人」 右幅:右上に落款「四明」、白文方印「男子生有四方志」 朱文方院「四明山人」 |
| 額 | 軸装 |
| サイズ | 各 / each : 108.2×45.8 cm |
| 文献 | 『蕪村展』、茨城県立歴史館、1997年、p.23、No.6 『蕪村全集 第6巻 絵画・遺墨』、講談社、1998、口絵、p.13、No.5 |
| 来歴 | 個人蔵、日本 |
HIGHLIGHT
与謝蕪村は、松尾芭蕉、小林一茶とともに江戸俳諧の巨匠と称されるが、俳諧師のみならず画家としても優れていた。また、独学で学んだ様々な表現を身に付け、詩情豊かな俳句を盛り込んだ「俳画」という境地を独自に開いた。代表作に芭蕉の俳句に挿絵を描いた「奥野道図巻」(安永七・1777年)がある。
与謝蕪村は芭蕉の没した22年後の享保元(1716)年、摂津国に生れ、本姓は谷氏(谷口氏とも)、後に与謝氏を名乗る。父が村長であったとも母は与謝郡出身ともいわれるが未詳。20歳頃に江戸へ出、京より江戸に移った俳人夜半亭宋阿(早野巴人)に入門し内弟子として居住、俳号を「宰町」と名乗った。寛保2(1742)年に27歳で師巴人が没すると江戸を離れ、同門の砂岡雁宕を頼り下総結城に赴き、そこを拠点に各地へ句作をしながら遊歴する修行の旅に出た。並行して絵画も独自に学び中国南宋画や、京の寺社、丹後や讃岐にて絵画の修行を行った。
本作は、結城下舘時期にのみ使用されたもの印章が捺されており、30代前後から後半の寛保二年から宝暦元年頃(cir.1742-1751)の作品であり30代後半の作と推察できる。中幅には赤絲の甲冑を付けた武将の前で文を書く人物、その衣の文様は胡粉のみの簡潔さがある。左右には、謡の扇子を手持ち、鼓を傍に置く人物、右の緋袴は金彩で輪郭をとり、上衣の模様や扇子や鼓に金泥使われている。一方左の人物は、緋色の上衣に金彩の千鳥文様が入った紗を重ね着し、萌黄の袴には蜘蛛の巣紋が金彩で描かれている。琳派の片鱗も見えるような不思議な構図である。画面に余白を十分にとったモチーフを配する素朴な構図のものが多く、後年のものに比較すれば、荒削りな中に味わい深さが感じられ、「てらいのない素朴な印象」を与える作風となっている。
この結城下舘時期は、いわゆる前作で、関東東北を遊歴した10年間と西帰し丹後に滞在した3年間を中心とした時期である。蕪村は、宝暦元年(1751)に京都へ至り住んだのち、宝暦4年(1754)丹後へ赴き宮津の見性寺に逗留した。宝暦7年(1757)の滞在の凡そ3年間、俳諧仲間との交流を持ち、数多くの絵画作品を残し、屏風絵も伝わっている。数多くの絵画作品を残し、屏風絵も伝わっている。その丹後時代の作品の和画系の作品のうち、《静舞図》(六曲半双)の静と女従者の袴、茶屋の店先とその前を往来する人々を描く《田楽茶屋図》(六曲半双)の人物表現には本作の人物画との類似性が認められる。また関東歴行時代(結城時代)に下館で描いた《追羽根図》(杉戸絵四面)とには本作との同一傾向があるため「結城下舘時期」の後半の作と推察できるであろう。