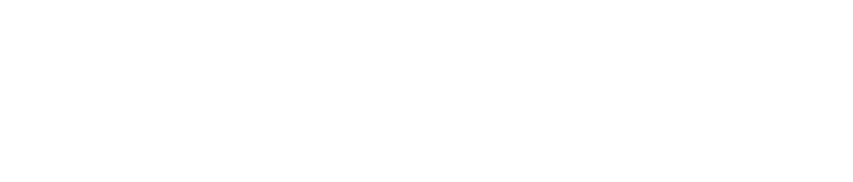東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 149
葛飾 北斎
雪中美人図 蜀山人賛
| 技法 | 絹本、著色 ※本作品は「重要美術品」指定作品のため、原則、国外への持ち出しは出来ませんのでご注意ください。 |
| サイン | 左に落款「前北斎 戴斗筆」、 朱文方印「よしのやま」 蜀山人賛「たをやめの あたゝかさうに見えたるハ 空にしられぬ 雪のはたえか」 箱蓋裏に「山王荘清玩」の貼札 |
| 額 | 軸装 |
| サイズ | 98.3×34.3 cm |
| 制作年 | 文化10-文政2年/cir.1813-1819 |
| 鑑定書 | 重要美術品等認定書付(發宗107號、昭和12・1937年5月27日発行) |
| 文献 | 永田生慈、『北斎肉筆画大成』、小学館、2000、巻頭の口絵、p.183&283、No.131 永田生慈、『浮世絵八華 5 北斎』、平凡社、1984、No.55 『山王荘蔵品展観図録』、大阪美術倶楽部、1935、No.111 『東洋美術大展覧会( 上巻)』、大阪市立美術館、1938、No.211 『肉筆 葛飾北斎』、金子孚水監修、毎日新聞社、1975、No.14 『北斎展』、東京国立博物館、2005、p.157 p.175、No.248 |
| 展覧会歴 | 『山王荘蔵品展観』 東京・大阪美術倶楽部、 昭和10(1935)年 『東洋美術大展覧会』、大阪市立美術館、 昭和13年(1938) 『北斎展』、東京国立博物館、2005年 |
| 来歴 | 福田政之助旧蔵 個人蔵、日本 |
HIGHLIGHT
本作は、雪中に佇む花魁を描いた、葛飾北斎による肉筆による美人画の代表作の一つである。後の「北斎ブルー」を思わせる鮮やかな青の着物を重ね、舞い散る雪をまとうすらりとした立ち姿。その背景に広がる胡粉により表現された雪景は、藍色の濃密な衣装と響き合い、雪降る静けさと清涼な気配を漂わせている。
描かれた女性は、おそらく吉原の花魁である。花魁とは教養、美貌、そして客をもてなす能力を備えた最高位の遊女で、その格の違いは、粋な着物や前結びの俎板帯、鼈甲や華やかな髪飾りなどの装飾品に表れている。着物は幾重にも重ねられ、外衣には濃紺の小袖(襟は黒)をまとい、内衣には表地に古渡唐桟(こわたりとうざん)、裏地に小紋模様や飛柄模様を配し、紅の総鹿子絞りをあしらっている。髪には花や鼈甲の簪を挿し、右手には黒と橙の蛇の目傘を携え、履物は黒塗りの高下駄に素足という出で立ちである。
衣をあえて簡素に、内衣を華やかに整えるこの粋な装いは、他の画家には真似のでき ない北斎ならではの美的感覚を示すものである。その奇想天外かつ巧緻なデザインには、『北斎模様画譜』に見られるテキスタイルデザイナーとしての資質が垣間見える点も興味深い。
細く小さな目におちょぼ口、そして乱れた一筋の髪。そのすべてが、この女性のしなやかなで艶のある仕草を際立たせている。足元は真冬でも素足、これは花魁の証でもあり、黒塗りの足駄に素足の美しさを線と色彩の妙によって巧みに表している。袖、襟、裾に施された絞りの技法は、質感と量感を巧みに際立たせ、降る雪や積もる雪の描写には微細な動きが感じられる。積雪の中を一歩一歩進む花魁の危うげな姿は、精緻な描写力を誇る北斎ならではの表現である。
落款は「前北斎 戴斗筆」、朱文方印「よしのやま」。北斎が「戴斗」の号を用いたのは文化7年(1810)から文政2年(1819)頃で、齢50〜59歳にあたる時期である。文化8年(1811)、52歳のときには「北斎改メ戴斗」と改号し、この時期には肉筆画においても数々の傑作を生み出した。
おおよそ文化3〜5年(1860-1809)頃を境に画風の変化が見られ、特に女性表現においては、いわゆる宗理風の特徴がある体躯が楚々として瓜実顔の可憐さを備えた姿から、体躯の豊かで艶やかな美人へと移行していく。本作はその変化を経た 50歳代(1813-1819)、北斎が到達した女性美の安定感と、いかにも垢抜けした内面的な魅力が余すところなく表され、まさに円熟期の美人画の秀作といえる。
また、戴斗期は《北斎漫画》を世に送り出し、西洋画法の研究と追求にも積極的に取り組んだ時期であり、その探究心と画技の成熟が本作にも色濃く反映されている。北斎は嘉永2(1849)年、90歳で生涯を閉じるまで精力的に制作を続けたが、本作はまさにその画業の中でも代表的な1枚であろう。