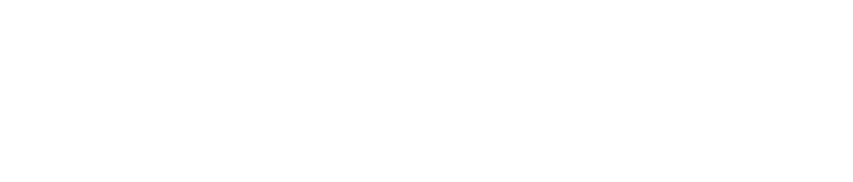東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 148
小林 一茶
自筆稿本「七番日記」 一茶愛用黒柿頬杖、一茶翁画賛幅付
| 技法 | 紙、墨書 全196頁 付門人文喬刻 黒柿製頬杖、 村松春甫画 一茶賛 一茶翁坐像 |
| サイン | 後跋 : 明治三十七・1874年六月日於東京下谷坂本町(無烏菴)中邨六左衛門利貞 蔵印 : 「大日本帝國信州柏原驛中邨」「利貞」、「信州佐久郡大田部村造化庵金石」、「瑞鷹館章」 |
| 額 | 冊子 |
| サイズ | 日記帖 / diary : h8.9×w18.7 cm 頬杖 / stick : L47.5 一茶翁画 /scroll : 117.6×36.0 cm |
| 制作年 | 文化7-15年 (1810-1818) |
| 文献 | 荻原井泉水編『一茶眞蹟集』 巧藝社、1937、No.193(七番日記)、203(一茶画像)、215(脇杖) <参考文献>『七番日記』 一茶同好會、會主 中村六郎、明治43年(1910) 『七番日記』 一茶同好会編集、目黒分店 戸田節次郎、大正11年(1922) 等多数刊行。 |
| 展覧会歴 | 長野県教育委員会、財団法人俳諧寺一茶保存会、信州善光寺、山ノ内町主催「一茶百三年忌記念展」、東京銀座三越、1956 <参考>信濃美術館友の会『一茶と藤村』、信濃美術館 |
| 来歴 | 信州柏原本陣中邨六左衛門家、造化庵金石、束松露香、瑞鷹堂(箱)、中村六郎利貞、個人蔵 日本 |
HIGHLIGHT
本作『七番日記』は、小林一茶(1763-1827)の文化7年(1810)元旦から文政元年(1818)12月に至る、48歳から56歳までの9年間にわたる句日記、自筆稿本である。日記と発句とを清記した一冊に一茶自ら『七番日記』と題した。七千首余りが掲載され、一茶の俳諧日記で最長であり最大の作品。一茶が郷里の柏原に戻った全盛期、52歳での妻を娶ったこと、4人の子をもうけて相次ぎ亡くし、若妻とにも先立たれるなどと、人生の最も変化に富んだ時期の句集日記の原本。巻頭には図書、頁の上段には日付、天気、日々の出来事、下段に俳句、俳文が連綿と記される。文化八年(1814)二月に「春風や牛に引かれて善光寺」、文化十二年四月「痩蛙まけるな一茶是にあり」等有名句も見える。後跋に柏原本陣の中村家、「一茶同好會」の発起人である中村六郎と佐久の俳人金石の蔵印が捺されている。この日記の後ろには、粉本をまとめた頁、中村六郎(利貞)による後跋と句数を数えた頁がある。
また本作には、門人文喬が彫刻した黒柿製の脇差を模した遺品の頬杖、同郷の俳人村松春甫の一茶翁像に一茶直筆の賛が添えられた掛軸が付く。
【遺物 脇杖】 林文喬作脇杖とは、脇息のように身をもたせたものである。武士などは脇差を立てて肘をもたせるが、その代わりのものとして、形も彫も脇差に擬えて作ったものである。材質は黒柿で、長さは47.5㎝(一尺五寸)、柄にあたる部分に「無代物」、裏に「正宗作」とある。名刀を作り上げた天下三作の相模の正宗を想起させ微笑ましい。鞘にあたる所に龍彫が施されており、「信陽柏原主林文喬作」の刻銘と「皐韋魚囝朔●(口の中に正)」と刻してあるが何かは不明。別に付属の春甫の「一茶翁画」の中にも、何か脇差のようなものが添えられているが、それがこの脇杖と考えられている。本作は、一茶同好會主 中村六郎(蘿月)による識箱「俳諧寺一茶翁座右頬杖」が付く。
【一茶画像】 松村春甫筆本作は、一茶存命時にモデルとして写された像であり、筆者の春甫は、長沼の人で一茶の門人として親炙していた上に、狩野派の画家であったため、この像は一茶翁を彷彿とさせるに最も近いものであろうと荻原井泉は述べる。上部に一茶の直筆の賛が添えられる。「やれうつな 蠅が手をすり 足をする」 「この句は、文政四年、一茶59歳の作であり、晩年好んで書いたものであるため、この像も60歳を超して、恐らくは還暦を祝う意味で描いたのではなかろうか。この一茶翁の左手に置いてあるものは、一茶が所持していた脇杖である(井泉水)。」
【一茶人物像】 小林一茶 は北国街道の宿場町柏原宿(現上水内郡信濃町)の豊かな中農に生まれた。幼くして母を失い、継母との関係が悪く、祖母の死後さらに関係が悪化し、江戸へ奉公に出された。25歳の時に、江戸の東部、房総方面を基盤とする葛飾派の俳諧師として記録に現れる。頭角を現した一茶は、東北、西国と俳諧行脚を行った。俳諧のみならず、古典、文化、風俗と多くを学び俳諧に反映させた。39歳で父を失い、継母と弟との間で十数年に渡る遺産を巡る争いが起きた。40代の頃には俳諧で生計立て葛飾派の枠を超え「一茶調」と呼ばれる作風を確立していった。その一方で、信濃で俳諧師として生活するために一茶社中を作っていった。51歳で遺産相続問題が解決し、故郷の柏原へ帰郷し定住することができ、父の遺産も相続し安定した生活を送る目途が立った。52歳の初婚で若妻菊を娶り、子を4人授かるも相次いで夭折した。この波乱の人生が、一茶40代後半から50代半ばまでの俳句日記『七番日記』として、赤裸々に描かれている。
その後の一茶の人生は不運に見まわれ、再婚するも破綻、体も発作を繰り返し衰弱、64歳で再々婚し、女児をもうけるも、亡くなる直前に家を焼失するなど不幸続きであった。人生の苦難の時期の俳句日記に「文化年中句日記・八番日記」がある。「九番日記」も存在するが、遺稿作品をまとめたものであるから現存する本作『七番日記』は貴重性が高い。直筆の俳句日記として、残る本作は、非常に貴重である。
一茶の名声は死後も褪せなかったが、門人から一茶調を引き継ぐものはなく小さなものになっていった。しかし、明治に入り正岡子規が発掘し、自然主義文学の興隆と主に、「生」をテーマとする一茶の俳句は再び脚光を浴びた。芭蕉、蕪村、一茶とともに江戸の三代俳人として称されるようになり、その句風は、人生苦や矛盾、弱者への寄り添い、子供や動物、自然を慈しむ目でもって「生」あることの尊さを詠みあげている。一茶調といわれる軽妙でオノマトペを多用した表現も他にはない魅力となっている。
村松春甫は、信濃長沼穂保(現長野市)の人。通称は煕、字は処信。俳諧を一茶に学び、菫庵・鷗巣・胡庵など号した。絵画を狩野興信に学び、色彩に優れ、花鳥画の名手であった。一茶の肖像として伝わるものは、ほとんどみな春甫の筆によるものと伝わる。文化七年に『菫草』の著あり、安政元年(1854)、年八十七で没した。
小林文喬は、柏原の人で、一茶の友人であった。また絵も描き谷文晁に師事し文喬と号した。一茶翁の為に脇杖を特製し、その没後、中邨家に継承されたと中村六郎(蘿月)の箱識にあり。
中村六郎は、明治元年柏原本陣中村家に生まれ、本名は六郎、号に蘿月(らげつ)。「一茶同好會」を組織し、多くの一茶遺品を蒐めた。大正13年(1924)に他界している。會主の中村六郎を中心に一茶同好會にて明治43年(1910)に、「七番日記」を書籍として編集発行した。一茶同好會の賛助会員に、文学博士や役人が載るが、夏目漱石、河東碧梧桐、巌谷小波、中村不折、男爵前島密(日本近代郵便の父)、平福百穂、長野市長鈴木小右衛門等が見られる。
〔参考〕『一茶眞蹟州』荻原井泉水、『一茶新考』矢羽勝幸、『俳諧寺一茶』束松露香