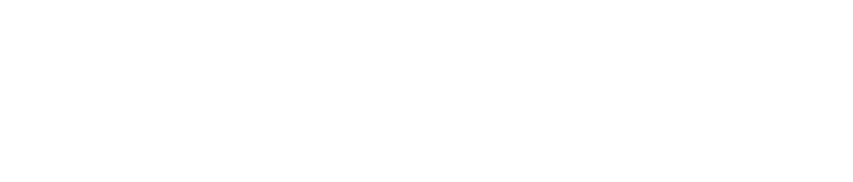東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 147
棟方 志功
運命板画柵・全4図 「黎明」 「真昼」 「夕宵」 「深夜」
| 技法 | 板画、マージンカット |
| 額 | 額装 |
| サイズ | 各 / each : 88.0×90.7 cm |
| 制作年 | 1951 |
| 鑑定書 | 4点ともに棟方志功鑑定登録委員会鑑定書、 棟方志功鑑定委員会登録証書付 「深夜」の柵に棟方巴里爾シール付 |
| 文献 | 『棟方志功全集第9巻 想いの柵(1)』、講談社、1978年、No.157-160 & p.192、No.113-116 《運命板画柵・美尼羅尼頌》 |
HIGHLIGHT
本作は『運命版画柵』は、別に『美尼羅牟(びにろん)頌運命版画柵』とも命名され、棟方が、昭和26年(1951)に疎開先の富山県福光町(現南砺市)より東京荻窪に再上京し手掛けた最初の作品で、4部柵として構成される。「運命」とは、ベートーベンの第五交響曲から主題とし、疎開先で読んだニーチェ全集から「ツァラトゥストラの巻、第一部序説一」を全面に彫制作したものである。
美尼羅牟(びにろん)(ビニロン)とは倉敷レイヨン(現株式会社クラレ)が、世界で初めて工業化に成功した合成繊維(PVA繊維、ポリビニルアルコール繊維)のことである。20世紀の巨匠作品を収集した倉敷大原美術館の創設者大原孫三郎と、その子息の事業讃えて制作された作品。大原父子とは昭和十三年(1938)に河井寛次郎に紹介されて以来、棟方の恩人であった。たまたま疎開先の富山の家に大原孫三郎が訪れ、「戦後の倉敷紡績の命運をかけて、新しい繊維を土台に大きな繊維の世界を作る。」という話を聞いた。棟方もこの仕事にこめる私の気持ちを表現できないか、私もベートーベンのような歓喜の仕事をしたいと申し出たところ、大原社長もベートーベンは好きなようで第五の運命をやってくれといわれたことが本作を作るきっかけとなったという。また仕事の題材にでもと、ニーチェのツァラトゥストラが版木に沿えて送られてきた。そして「日本のため世界のため、ビニロンをつくらなければならない。そのため導きの火がいるのだ。運命という題下に、ツァラトゥストラは超人を中心人物にしているのだから、超思想というような大きなものを版画でつくってほしい。」と大原社長から言われたと棟方は記す。ツァラトゥストラを読んだ棟方は、「なるほど、えらい大きい規模と、孤独というのか、何ともいえない大きい世界にひきいれられてしまいました。これはこまかい仕事になってはいけないから、それだけ一つという行き方でやろう。」と彫刻刀は四分丸刀を一本だけ用意し、二日ばかり考え、三日目から彫り始めた。版木4枚ずつ4図、全部で16枚の板木、それぞれ「黎明」「真昼」「夕宵」「深夜」の図柄を、板木を真っ黒に塗って、丸鐫だけで版木に直接下絵を作っていく、丁度エッチングで銅板に蝋を塗り針で彫って行くように、下絵板画となり、間違えればそれっきりといったやり方で、一気呵成に仕上げていった。
一図「黎明」には、ニーチェが海抜六千フィートのエンガディーン地方のシルス・マリアの森のほとりのシルヴプラーナ湖岸の巨岩の陰で出会ったというツァラトゥストラの立像に、鷲と蛇を従えて、ツァラトゥストラが洞窟の中から星をのぞみ、おお星よ、とつんざくような叫びをあげている感じを出し、二図 「真昼」には、太陽の内輪に鳥の群れ、太陽にいる烏、三本足という伝説の烏を、太陽の形どった、丸い偉大な光の外側に、羽をひろげさせてつながらせた。第三図「夕宵」は、上下左右に裸婦を、裸の女体を、やはり丸い形にして、天に遊んでいる姿にしたく作る。その女人達はみな行儀よく坐っている、それは夕宵の静まってゆく静止の姿を出そうとした。第四図「深夜」は眠れるツァラトゥストラを横たえた図。ツァラトゥストラが天から没落しつつある姿体を一杯にあらわし、ここに始まる幸の象徴にしようとしたと棟方は語る。
ビニロンができた祝いの会では、床の間にこの版画をかけ茶のもてなしを受けたという。大作の4枚のため、全部揃えて飾ってもらいたいと考えた棟方は、湊川神社に奉納し、現在でも拝殿天井画として4図が掲げられている。本作は、フランスのサロン・ド・メ(毎年五月に行われる前衛芸術の展覧会)に出品、棟方にとっては三度目の渡仏作となった。最後に、棟方は、この作品は「ほかの板画とちがい、摺りによって、生きるか死ぬかの板画で、刷毛バレンの難しい作品」と語っている。(昭和31年刊《版画の道》より。)
ツァラトゥストラは三十歳の時、其故郷と其故郷の湖とを去りて山に入りぬ。その処にその精神と其孤独とを享楽し、十年を経て倦むことなかりき。されど遂に、彼の心機は一転せり。ある日の朝、黎明と共に起き出て、太陽の前へ歩み寄りて、斯く波は太陽に語りき—―『汝、大なる星よ。汝によりて照らさるるところのものなくば、何の幸福なることか汝にあらむ。十年の間を、汝はこの我が洞にのぼり来りき。我と、我が鷲と、また我が蛇とのあるにあらずば、汝は其光と其道とに倦じたりしなるべし。されど我等は朝毎に汝を待ち、汝の横溢を受け、その事の故に汝を祝福せり。見よ。わが我自らの叡智に倦じたるは、あまりに多くの蜜を集めたる蜜蜂のごとし。我はこれを得むとて差し伸べらるるところの手をもとむ。我は賢き人々が人々の間に今ひとたび自らの富めるを悦び、貧しき人々が今ひとたび自らの富めるを悦ぶに至るまで、我自らの有てるものを配ち与むことをねがう。されば汝が夕々に、海のあなたへ入りつつも、光を幽界に齎すときのごとく、我もまた深きところへ降り行かざるべからず。汝、豊饒なる星よ。我は汝のごとく没落せざるべからず(わが降り行かんとするところの人々、これを称して没落という。)されば汝、其大の幸福をも嫉視することなき平静の眼、われを祝福せよ。将に溢れんとする盃を祝福せよ、金色なる水のこれより流れ出で、汝が悦楽の反照を到る処に運び行かんことの為めに盃を祝せよ。見よ。此の盃は再び空しからんとす。而してツァラトゥストラは再び人間にならんとするなり。』――斯くしてツァラトゥストラの没落は始まりき。
大原孫三郎(明治13年-昭和18年/1880-1943)、岡山県出身の実業家、社会事業家。倉敷紡績の経営、大阪に大原社会研究所を設立し、社会問題の研究にあたらせた。倉敷に大原美術館等を開設するほか、昭和11年には柳宗悦らの日本民藝館開設にも援助を行うなど文化に多大の貢献をした。
大原総一郎(明治42年-昭和43年/1909-1968)、実業家。祖父孝四郎、父孫三郎のあとを継いで昭和16年に倉敷紡績の社長となる。大原美術館理事も歴任。
ツァラトゥストラは「ツァラトゥストラはかく語りき」で、詩の形で書かれたニーチェの主著。権力への意志、永劫回帰、超人の思想を説く。ツァラトゥストラはゾロアスターのこと。
生田長江(明治15年-昭和11年/1882-1936)は鳥取県生まれの評論家、小説家、戯曲家、翻訳家。