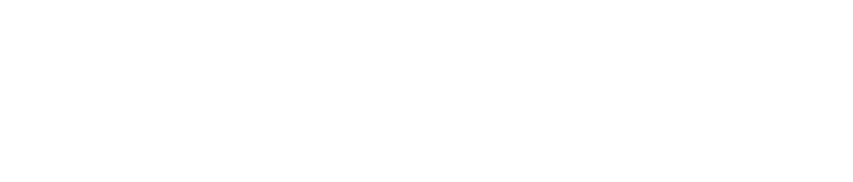東西ニューアート 設立記念公開オークション
LOT 118
安井 曾太郎
鯛
| 技法 | 油彩、キャンバス |
| サイン | 左下にサイン、年代 |
| 額 | 額装 |
| サイズ | 49.0×59.5 cm |
| 制作年 | 1953 |
| 鑑定書 | 東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付 共板 安井はま鑑題シール |
| 文献 | 『安井曾太郎遺作展図録』、1956、No.273 |
| 展覧会歴 | 『安井曾太郎遺作展』、1956年、東京国立近代美術館 |
HIGHLIGHT
テーブルに置かれた皿からはみ出すほどの大きな鯛が、右から左上へ頭を向ける構図で描かれている。さらに、皿を載せたテーブルをわずかにずらし、金茶色の床板の板目を画面に取り入れることで、俯瞰的な視点が生まれている。この独特の構図が、安井曾太郎の表現の豊かさをいっそう際立たせている。安井はしばしば、身近な人から贈られた果物や花などを題材に静物画を制作したことが知られている。しかし油彩による制作には時間を要し、その過程で花は変色し、枯れ落ち、果物は腐食してしまうことになる。
本作品と同様に「鯛」をテーマとした作品が静岡県伊豆下田市の「上原美術館」(大正製薬株式会社名誉会長・上原昭二氏より寄付を受けた近代絵画コレクションを展示する私立美術館)に所蔵されている。「銀化せる鯛」(65.0x54.0cm)とされた作品は本作品と酷似するもので制作年も同じである。美術館の解説によれば、「正月に知人から贈られた新鮮な鯛を、異なる角度から鮮やかな色彩で描いた。中略。再び描き始めてからは、5月までアトリエに置き続けた」と記されている。このため、当初は赤々とした鯛が、やがて腐敗して干物のようになってしまったという。
作家自身も「油絵で鯛を描くのは初めてで、思うようにいかず日ごとに制作がのび、≪モデルの鯛≫はすっかり干物になってしまった。だがそれは実においしく、また立派な銀の彫刻のようにも見えた」と語っている。さらに、描き終えた鯛について「哀れに思い、家族とともに皿ごと山中に丁重に埋葬した」とも回想している。安井曾太郎が静物画で「魚」を描いた例はきわめて珍しく、その意味で「銀化せる鯛」と並ぶ、あるいはそれ以上に希少性の高い価値を持つ作品といえる。
また、本作品は、没後(翌年)の「安井曾太郎遺作展(東京・京都で開催)」に出品されており安井曾太郎作品の中でも評価の高い作品として認知されていたことが伺える。